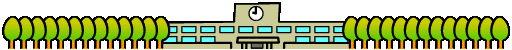
![]() 「技能教科の授業」のこつ
「技能教科の授業」のこつ
よくありがちな失敗。
まずは一斉授業。
習熟のために練習問題をやらせる。
そして計算問題が早く終わった子。
次の課題を指示しつつも、個別指導な子に気を取られている。
できる子はどんどん進む。
結果、やることが無くなって遊んでしまう。
最近の私。
まずは一斉授業。
この時、全員が理解できているわけではないのは当然。
でも、数名でよいから確実に理解できる子が出るようにする。
そして、習熟のために練習問題をやらせる。
計算問題が早く終わった子。
次の課題を指示。それもクリア。
そこで一言。
「じゃあ、君は先生になって。」
その子は嬉々としてよく理解できない子どもたちに教えます。
私がやりたかった個別指導です。
しかし、私の体は一つしかありません。
練習問題を終える子が増えれば増えるほど、
よく理解できない子どもたちにとっては機会が増えます。
このような学習形態が、自分の中でようやく形になってきました。
グループ学習、班別学習、教え合い学習、
いろいろな学習形態があるし、知識としては知っています。
今までずいぶんやってきました。しかし、知識と実践は違います。
例えばおしえ合い学習を、どのように授業に組み込むか。
自分に一番あったやり方は、上記の方法でした。
私一人ががんばっても、学級の子どもたち全てができるようになりません。
一人に1分教えるとしても、30人いれば30分待ちです。
だったら、個別指導は子どもたちに委譲してしまおうと。
そうすれば、子どもたちの待ち時間は減ります。
待ち時間が多い授業は、非効率的です。
子どもは飽きるし、それで説教することになるし、いいことはありません。
ただし、個別指導を子どもたちに委譲してしまっても、
教員としてそれを掌握する必要はあります。
「こういう言い方をすると理解しやすいよ。」「もう少し考えさせて、君は待ってごらん。」など。
人に教えると、知識はより深まります。
相手のつまずきを見抜けなければ、本当に理解したことにはなりません。
教える側、教えられる側、ともに勉強になります。
やがて大多数の子が理解できるようになると、
教える子どもの役割は終わってしまうかに見えます。
しかしここでまた、権利の委譲。
「丸つけしてあげて。」
机を前に持ってこさせ、丸つけをしてもらいます。
こうすることで、行列ができ、並んでいる最中に飽きておしゃべりすることもありません。
課題が終わった子は教えたと思ったら今度は丸つけ、
暇にはなりません。
その間に、私は私が直接教えた方が効果が上がる子に指導できます。
最近、教員の技能って、単に勉強を教えられると言うことではないと思うようになりました。
おもしろい授業、工夫した教材、それも確かに必要なのですが、
学習の流れを作る、ということも、とても重要に思います。
担任はいつまでも勉強の面倒を見られるわけではありません。
しかし子どもたちは、何年たっても同年齢の集団として、仲間であり続けます。
だからその人間関係に、遊び集団としてだけでなく、学習集団としての形を整えることが、
とても重要だと思います。
だからあえて、教員が勉強を教える必要はない。
勉強を教えられる子どもがその力を生かし、
先生を必要としてる子どもに、
より多くの子ども同士の教え合いによる先生を確保する流れを作ることが必要なのではないかと。
本来ならば、10人程度の集団に1人の教員、くらいの割合でなければ、
きめ細かな指導などできません。少人数であるほどよいです。
しかし、少人数の編成など、政治・予算的な面から考えて、
現状ですぐに対応できる問題ではありません。
ならばすぐに対応できる手段として、子どもの力を生かすということを私は考えます。
もともと人間集団は、能力に差のある集団です。
全員が均一であることなど不可能だし、
能力が均一である集団は、それ以上の刺激がないために停滞します。
それぞれの子どもたちが長所を生かし、互いの短所を補い合うというのが、
人間集団として、もっとも自然な状態です。
その自然な状態を保つことこそ、教員のもっとも重要な仕事ではないかと思うのです。
 「まじめなお話の間」トップへ
「まじめなお話の間」トップへ