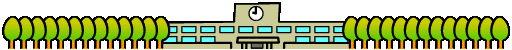
![]() 「とか」とか
「とか」とか
日本人は物事を断定的に言い切ることを避け、曖昧表現を使うことが多いです。
などと「言い切って」しまうと「必ずそうなのか?」と批判をされてしまうことも考慮して、
「多いようです。」と書くように勧められます。これも断定を避ける日本人の曖昧表現です。
若者言葉として眉をひそめられてしまいがち(→断定を避けている)な言葉は、
実は日本古来の曖昧表現の例から外れていない場合が多いようです。(→断定を避けている)
1.「〜とか」「〜し」
お菓子屋さんで。「お菓子とかやります?」「お菓子しかねーよ!お菓子屋さんなんだからよ!」
薬屋さんで。 「薬とかあります?」「薬しかねーよ!」薬屋なんだからよ!」
鹿屋さんで。 「鹿とかあります?」「鹿しかねーよ!」鹿屋なんだからよ!」
「とか」を聞く度に、こんな風に思ってしまうのですが、本来は、
「ラムネとか、チョコとか、クッキーなどありますか?」と並列で使う言葉です。
「知ってるしぃ。」
「し」も並列表現ですね。
「あれもしたし、これもしたし、それもした。」と使うべきで、単体で使う言葉ではありません。
2.「〜的に」
「〜としては」でしょうねぇ。
3.「○○さんの携帯でよろしいでしょうか?」
携帯はしゃべりません。私は私。人間です。
それに、もし私が○○さんの携帯を借りていたなら、
「これは○○さんの携帯ですが、私は○○さんではありません。」と応えることになるでしょう。
4.「〜の形になります。」
セールス電話や詐欺師はもちろん、一般のお店でも使われてきている言い方。
「お値段が○と○と○で、こういう形になりますがよろしいでしょうか?」
こういう形って三角?四角?いやぁ、私は丸の方がいいんですけど…。
○○円ですと、普通の言い方でいえばよいのに。
5.「よろしかったでしょうか」
確かに「よろしかった」と思ったけど、今はよろしくない!と、注文を取り消しやすくするための思いやり?
6.「〜じゃなくね?」
二重否定。しかしこの言い方はとても便利で、
相手が自分の意見と同意ならば「そうだね。」と返答し、
相手が自分の意見と反対ならば「そんなことないよ。」と返答し、
どちらに返事が来たも対応しやすい言い方です。
コールドリーディングで、いかにも相手の心を読んでいるかのように問いかける時にも使う方法だそうです。
さらに「〜じゃなくね?」という言い方はちょっと茶化した、ちょっと砕けた言い方で、
相手に対して敵意を向けるというよりも、共感的な位置にいる言い方です。
断定的な言い方を避け、曖昧な表現をする、現代の若者ならではの、
否、日本人の性質が見事に次世代に受け継がれ、変貌を遂げた言い方、と言えるかもしれません。
7.「少しづつ」
これはもう、ローマ字入力の弊害としか思えません。
テレビのテロップ、雑誌、レストランのメニューなど、至る所で見かけます。
正しくは「ずつ」でしょう。しかし、ローマ字入力をした場合、「ず」と「づ」の打ち分けはあまり意識しないのかもしれません。
かな入力の私には、知るよしもありません。
8.「ダサ」「キモ」「速っ」「うまっ」
牛肉を食べていて、「うまっ」って、馬肉じゃねーよ!
どうも最近形容詞の活用語尾が省略されてますね。
「い」なんて一文字なんだから、発音してあげましょうよ。
「キモ」って、「きもちわるい」の省略形のつもりかもしれないけれど、
「きもちいい」も同じルールで省略すると、「キモ」になります。
そもそも「キモ」は「肝」であって、「肝心」という意味。
「そこが肝なんだよ。」と正しい使い方をすると、ひょっとしたら「気持ち悪い」といわれたと誤解されかねません。
それとも「キモ」って、レバーのこと?レバーが食べたいの?鉄分を補給するにはよいでしょうね。
このままでは、日本語は危ないのではないかなあ…。
といいつつ、自分の日本語も、昔の人からしてみれば、おかしいのかもしれません。
 「まじめなお話の間」トップへ
「まじめなお話の間」トップへ